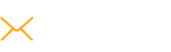相続コラム
2025/05/07 相続ガイド
相続ガイド②「期限がある手続き」

【10日以内】にするべき手続き
死後10日以内が期限の手続きがあるため、【期限14日以内】の手続きもまとめて【10日以内】と表記しています。
手続きの期限の目安として参考にしてください。
手続き先は、主に
1.亡くなった人の本籍地か住所地の役所
2.最寄りの年金事務所
3.最寄りの警察署
上記の3か所です。
手続き先ごとに、それぞれどのような手続きを行うのか確認していきましょう。
1. 亡くなった人の本籍地か住所地の役所で行う手続き
役所では、除籍謄本(死亡の事実が記載された戸籍)を取得します。
下記記載の戸籍が必要になる手続きが多いため、その役所で取得できるものがある場合は、あわせて取得しておくと手間が省けます。
・被相続人(亡くなった人)の出生~死亡までの一連の戸籍
・相続人全員の婚姻~現在までの一連の戸籍
・被相続人の住民票除票もしくは附票の除票
・相続人全員の住民票もしくは附票
※住民票と附票はどちらを取得しても構いません。
※附票は認知度が低い書類ですが、戸籍と同じ申請用紙で申請できるケースが多く、住所の変移もわかることから住民票より附票の取得をおススメします!
以下、その他の手続きです。(該当する手続きのみ行ってください。)
・健康保険証の返還、資格喪失届の提出
・葬祭費支給申請用紙の取得
・高額療養費支給申請用紙の取得
・介護保険証の返還、資格喪失届の提出
・世帯主変更届 ・児童手当の申請
・送付先変更届の提出
・還付金の申請
・障害者手帳の返還
・未払い手当等の申請
各手続きには、10日以内または14日以内などの期限がありますが、過ぎてしまったからといって罰則はありません。
しかし、手続きしなかったり放置したりしてもメリットはないため、忌引きなどで時間が取れるうちに手続きしておきましょう。
手続きによっては必要書類もあるため、事前にHPや電話で確認し、用意をしてから役所で手続きしましょう。
また、担当窓口が分からない場合は、いずれかの窓口で手続き内容を伝えると案内してもらえるため、その案内に従い順に手続きを進めます。
【参考】
高崎市 ご遺族支援コーナーのご案内(死亡に伴う各種手続きのご案内) – 高崎市公式ホームページ
前橋市 ご遺族の方へ/前橋市
伊勢崎市 おくやみ相談窓口を開設しています/伊勢崎市
藤岡市 おくやみ窓口/藤岡市
2.最寄りの年金事務所で行う手続き
亡くなった人の住所地にある年金事務所に出向き、年金に関する手続きを行います。
主に下記記載の3点が必要になります。
・年金受給者死亡届の提出
・未支給年金の請求
・遺族年金の請求
※年金を受給中だったのか、年金を納めていたがまだ受給前だったのか、個々人の状況によって必要な手続きは異なります。
亡くなった人と一番近しい人があらかじめ年金事務所に電話をし、基礎年金番号やマイナンバーを伝えて必要書類などを確認するとよいでしょう。
【参考】 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構
実際の手続きは、窓口または郵送となりますが、人によって手続き内容も必要書類も変わってくるため、窓口で案内を受けながら手続きすることをおススメします。
3.最寄りの警察署での手続き
亡くなった人が運転免許証を所持していた場合、最寄りの警察署に出向き、運転免許証を返還します。
その際は死亡診断書が必要となるため、あらかじめ取っておいたコピーを持参しましょう。 (ただ、返還せずとも罰則などはないため、手続きせずそのまま手元に残しておく人もいます。)
在職中に亡くなった場合は、健康保険、年金などの手続きは、会社を経由して手続きすることが多いです。
よって勤務先に死亡の連絡を入れる際に、これらの必要な手続きについて案内してもらうよう申し添えておきましょう。
4.【その他】の手続き
①各種サービスの解約
利用していた各種サービスの解約や名義変更など期限は決まっていませんが、なるべく早めに故人様の各種サービスを解約し、 口座やクレジットカードからのお金が引き落とされるのを防ぐとよいでしょう。
忘れがちなのは、月額や年額で課金制のサブスクリプションの解約です。
見落としのないよう確認しましょう。 引き続き利用するのであれば、名義や引き落とし口座などを変更します。
また、故人のクレジットカードで家族カードを作成していた場合、 紐付けられているカードも使えなくなるので注意しましょう。
・携帯電話の解約 ・電気、ガス、水道の解約、契約者名義変更
・新聞、インターネットの解約、名義変更 ・クレジットカードの解約
・保険契約の解約 ・その他契約しているサービスすべての解約 など
②生命保険の手続き(死亡保険金)
生命保険の保険証券や契約内容のお知らせがある場合、その用紙に契約内容が記載されているため確認します。
死亡保険金については、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」が記載されており、その「保険金受取人」に指定されている人が、手続きをする人になります。
※「保険金受取人」が指定されていない場合は、保険会社の規定に沿って受取人が決まるため、その方が手続きを進めます。
保険請求をして保険金が振り込まれるまでに2~3か月かかるところもあるため、早めに手続きを進めましょう。
連絡先は保険証券に記載されている連絡先、または代理店を通しての手続きになります。
保険契約によっては入院給付金の請求が可能な場合もありますが、これは本来亡くなった人自身が請求するもの(=亡くなった人の財産)であるため、相続財産になります。
よって、相続人が確定してからの受け取りになるため、死亡保険金と切り離して手続きをすることになります。
【1ヵ月以内】の手続き
1.雇用保険受給者資格者証の返還
故人が雇用保険(失業給付など)を受給していた場合、死亡後1ヶ月以内に、雇用保険受給資格書を受給していたハローワークに返還する必要があります。
【3ヵ月以内】の手続き
1.(相続放棄する場合は)相続放棄
原則として「死亡後3ヶ月以内」に相続放棄しなければならないと考えておくと、期限を過ぎてしまうことを防ぐことができます。
なお、3ヶ月の期限を過ぎる前なら、一定の要件を満たして裁判所の許可を得れば期限を延長できることもあります。
ただし、単に忙しかったという理由だけでは延長できないなど、延長できるケースは限られていますので、相続放棄するのであれば早めに手続きをした方がよいです。
借金だけを残して亡くなった場合や、プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、そのまま相続をしてしまうと故人の借金を代わりに返す必要があります。
故人の借金を返すのは経済的に負担が大きいので、相続放棄を検討することが多いです。
詳しくは弁護士へ相談すると良いでしょう。
2.死亡後の手続き(期限なし)
相続放棄をしない場合は、預貯金の解約や株式、不動産の登記手続きなどを行う必要があります。
相続税の申告・納税の期限(死亡後10ヶ月以内)までに終えるとよいでしょう。
金融機関から故人の預金を引き出したり、不動産の登記手続きをしたりするのに、相続が生じたことや相続人が誰かを明確にするための書類が必要となります。
その場合は、「法定相続情報証明制度」を利用するとよいでしょう。
法定相続情報証明制度を利用することで、法定相続情報一覧図の写しが無料で交付され、個人の銀行口座の解約等に際し、故人の戸籍謄本(除籍謄本)を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは弁護士に相談すると良いでしょう。
【4ヵ月以内】の手続き
1.所得税の準確定申告・納税
故人が個人事業を営んでいた場合、相続人はその故人の代わりにその年の確定申告を行います(これを「準確定申告」と言います)。
この申告は、1月1日から死亡した日までの所得・税額を申告することによって行います。
【6ヵ月以内】の手続き
1.未支給失業等給付請求
故人が、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中や雇用保険の他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる場合は、故人と生計を同じくしていた一定のご遺族は、死亡日の前日までの基本手当 (未支給失業等給付)をもらうことができます。
【10ヵ月以内】の手続き
1.相続税の申告・納税
期限までに相続税の申告・納税をしなければ、加算税・延滞税などがかかることがありますので注意しましょう。
複雑な場合もあるので、税理士などに相談するのが良いでしょう。
【1年以内】の手続き
1.遺留分侵害額請求権
本来は法定相続人であるのに、遺言により他の人に全ての遺産を贈ることとされていたなど、遺言によって十分な遺産を相続できない場合に選択できる権利です。
相続を扱う弁護士に相談・依頼して行うのがよいでしょう。
以上が葬儀後の手続きとなります。
複雑に見えますが、各手続き先で案内してくれる内容も多いので、まずは問い合わせてみることが大切です。
当センターでは、ご自身で各手続き先に行く必要がなく、当センター窓口のみで手続きを完了することができます。
手続きに時間が取れない、内容が難しいなどございましたら、気軽に無料相談をご予約ください。
※ここではお伝えしきれていない「預貯金の解約」や「株式」など各手続きの詳細は、今後の「相続ガイド」でご案内いたします。

各手続きについてイメージはできたでしょうか?
相続手続きには相続人全員の承諾が必要な手続きが多く、相続人との話し合いをする機会が多くなります。
次回「相続ガイド③」では相続人の確認についてご案内いたします。
ご自身が誰と話し合いが必要になるのか、是非ご確認ください。


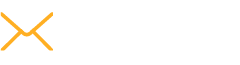
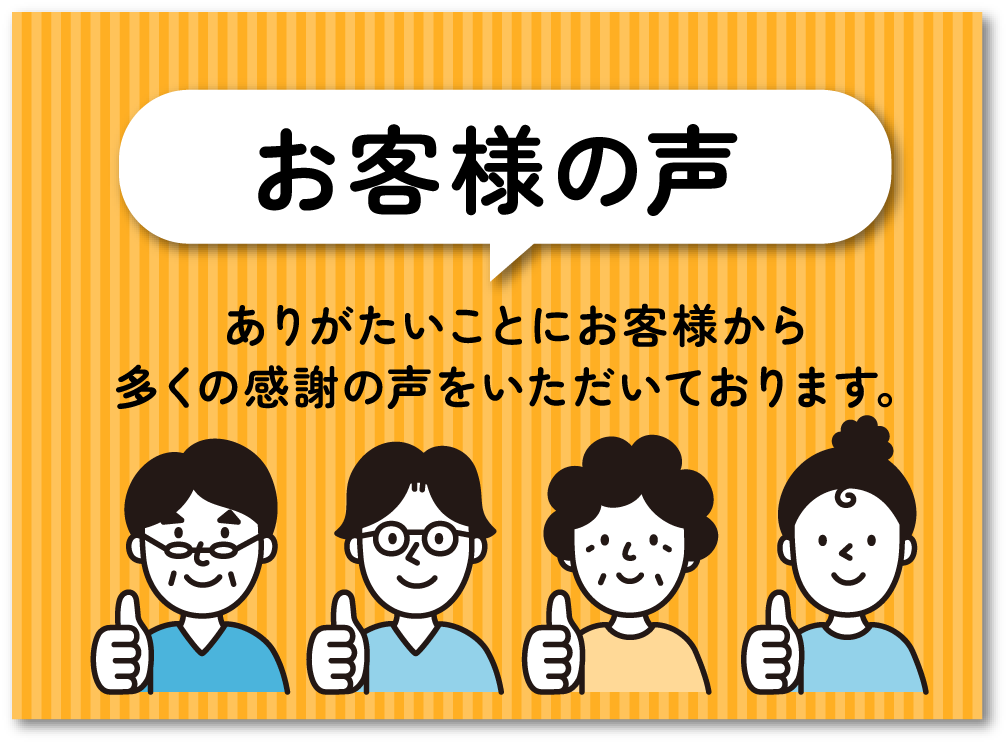
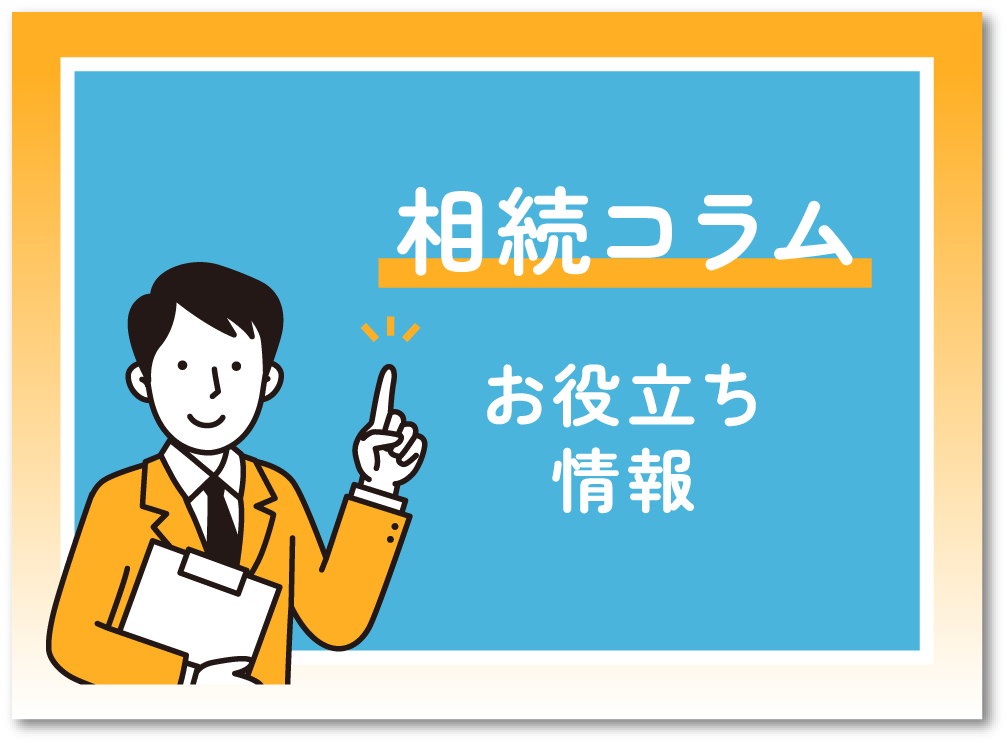

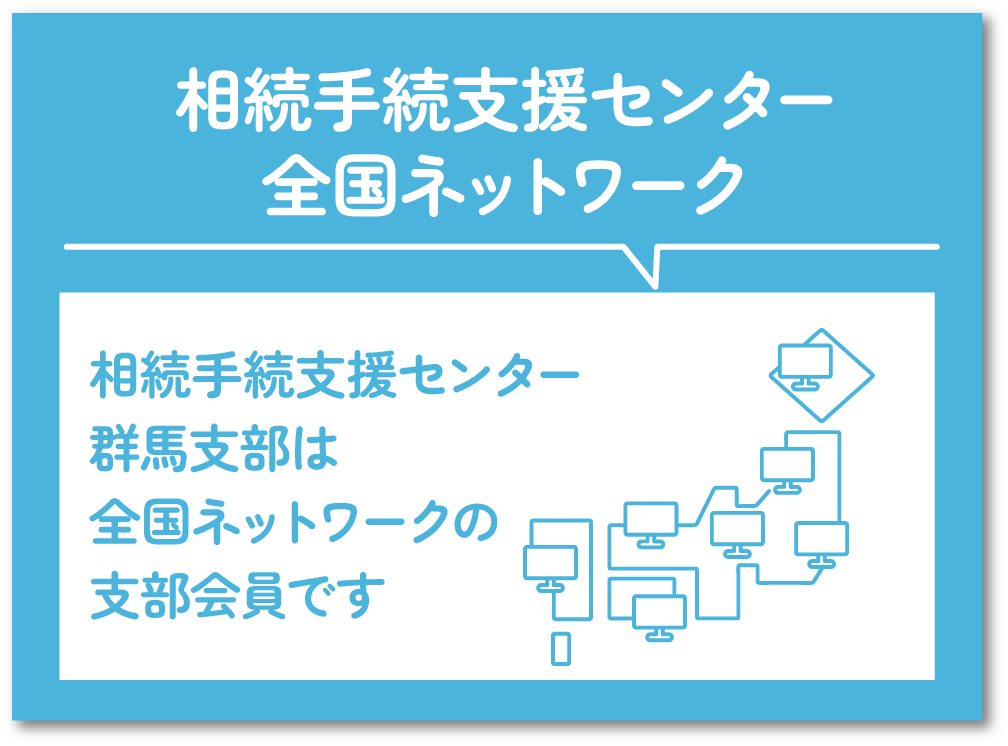
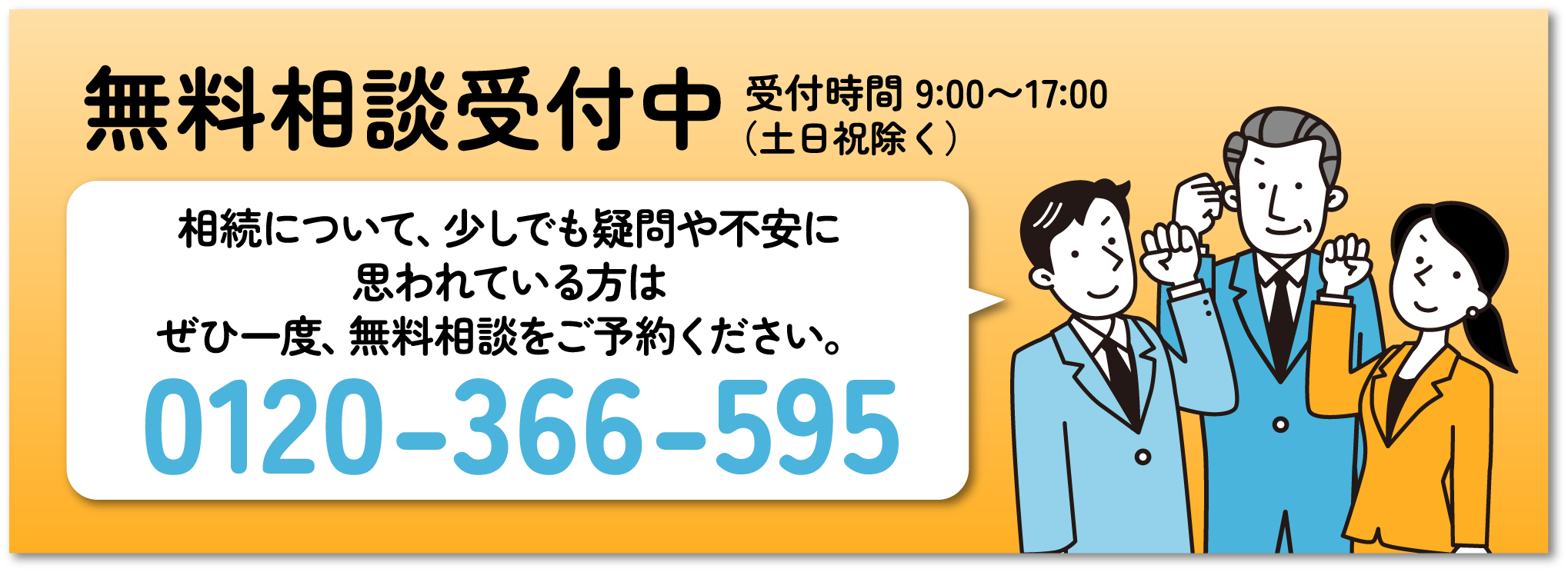

 通話無料
通話無料
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ