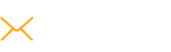相続コラム
2025/08/25 相談事例
相続人がもう一人
上野さんは、母Aさんが亡くなり相続手続の相談に来られました。
相続人は上野さんと妹のBさんで、父Cさんは既に亡くなっているとのことでした。
早速戸籍を集めて確認すると、亡くなった母Aさんには死別した前の夫・甲さんとの間に産まれ幼くして2才で亡くなった子供・乙さんがいたことが分かりました。
上野さんの母Aさんにとって、父Cさんとの結婚は2度目だったのです。
上野さんと妹Bさんは2人とも、母Aさんと父Cさんとの実の子供です。
ここまでなら、すんなり上野さんとBさんだけが相続人になります。
しかし、実は母Aさんが父Cさんと結婚する前に養子丙さん(女性)を受け入れていたことがわかりました。
相談員がこのことを上野さんに聞くと「母から聞いたことがあるけど、もう離縁しているはず」とのことでした。
しかし、戸籍を調べても離縁の事実は出てきません。丙さんはご存命なら80歳です。
そこで上野さんに丙さんの戸籍の附票を取ってもらいました。
すると丙さんの現在の住所は石川県にあることが判明しました。
上野さんも面識はありません。
上野さんは、丙さんに事情を綴った手紙を出すことにしました。
ただこの時点で、相続税の申告期限まで1か月を切っていました。
やむを得ず全ての財産について未分割として相続税の申告をし、丙さんの分の納税は上野さんが立て替えました。未分割では小規模宅地の特例が適用できないので、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、分割後に更正の請求をすることにしました。
そして1か月後丙さんの息子と名乗る方から連絡が入り、丙さんは元気であること、養子の事実にびっくりしたことを話されました。
幸い、丙さんも息子さんもとても温和な方で、特に遺産分けの要求もなく遺産分割協議書への署名押印に応じてくれました。
この遺産分割協議の結果をもとに小規模宅地の特例を適用した更正の請求をし、過大となっていた納税額を還付してもらうことにしました。
未分割で申告した際に立て替えた納税額70万円は税務署としては丙さんが払ったものなので、丙さんの銀行口座への還付となります。丙さんに返金してもらう手間がかかります。
上野さんは「これも何かの縁だから」ということで、その70万円は遺産分割協議のいわゆる「ハンコ代」として丙さんに相続してもらうことにしました。
母Aさんの最初の婚姻の夫甲さんは結婚の翌年、子乙さんは結婚の3年後に亡くなっています。今回相続人と判明した丙さんが母Aさんと養子縁組したのは、子乙さんが亡くなった2か月後(昭和13年)です。この時代であれば跡取りとして養子を迎えることもあったでしょうが、丙さんは女性です。今となっては養子となった理由は分かりませんが、出来る限り親の戸籍は生前に見ておきたいものです。
(486)


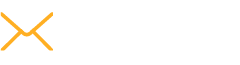
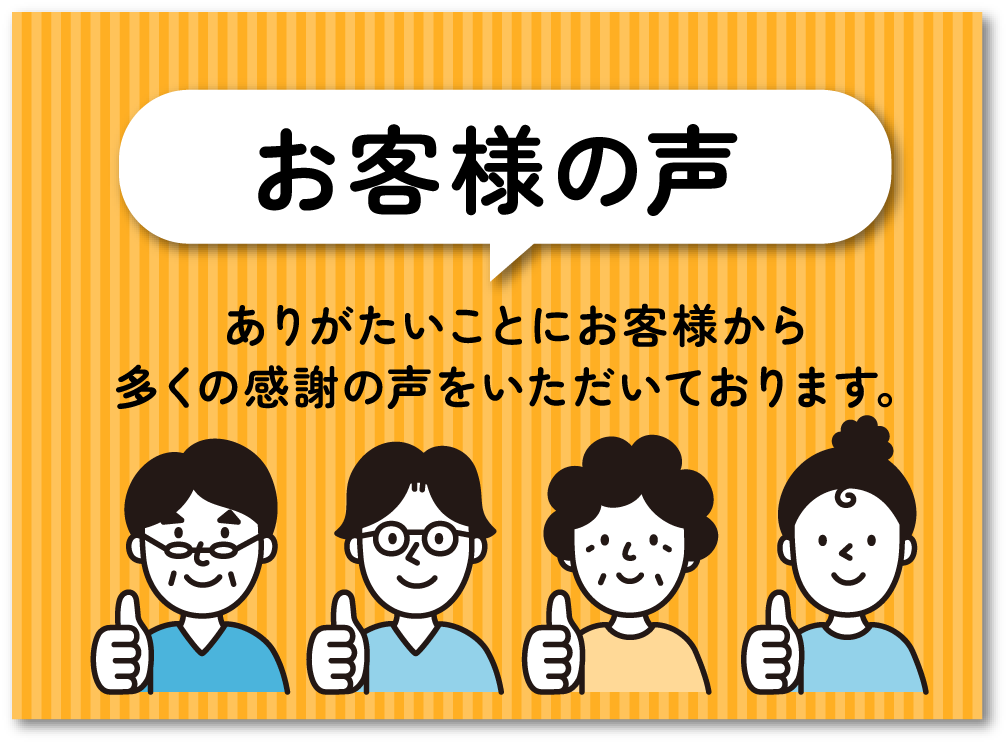
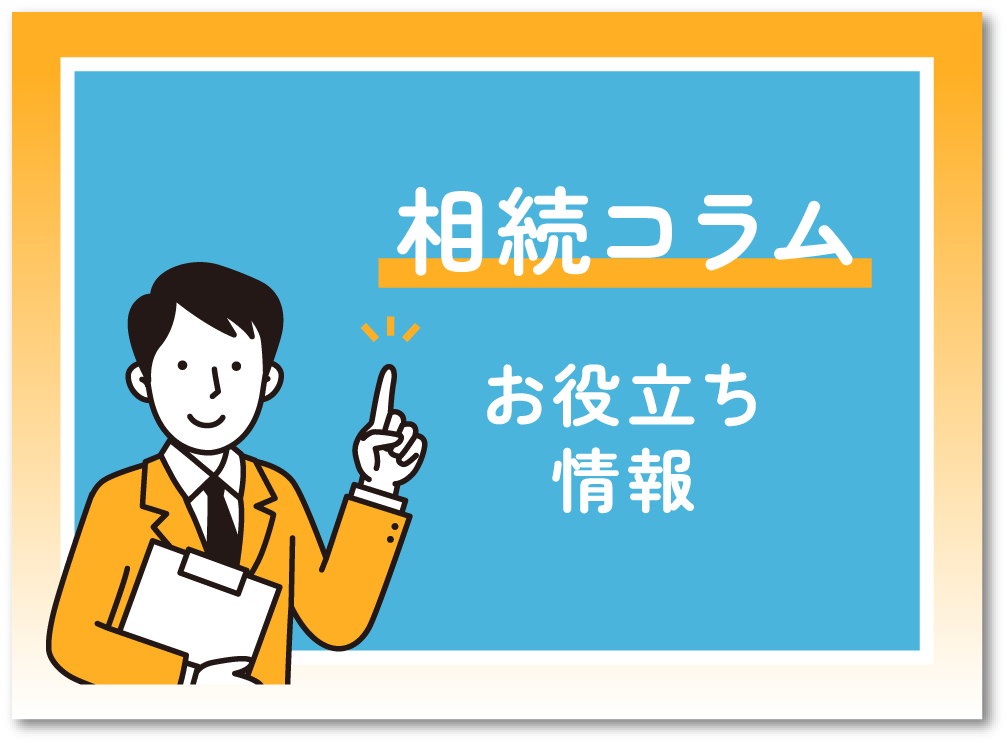

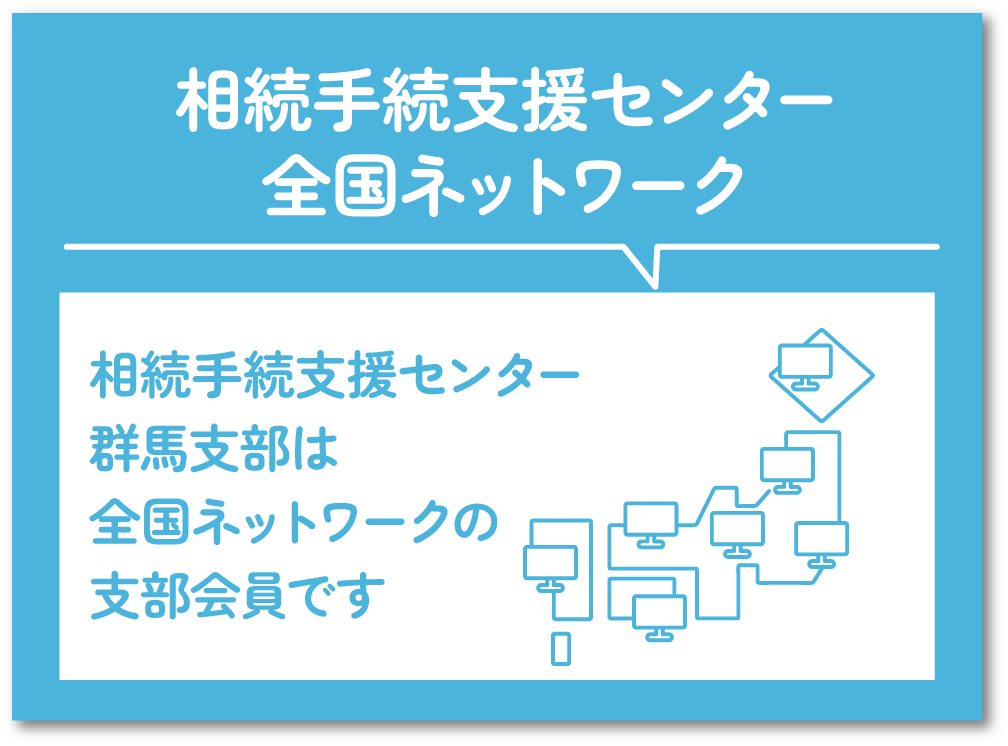
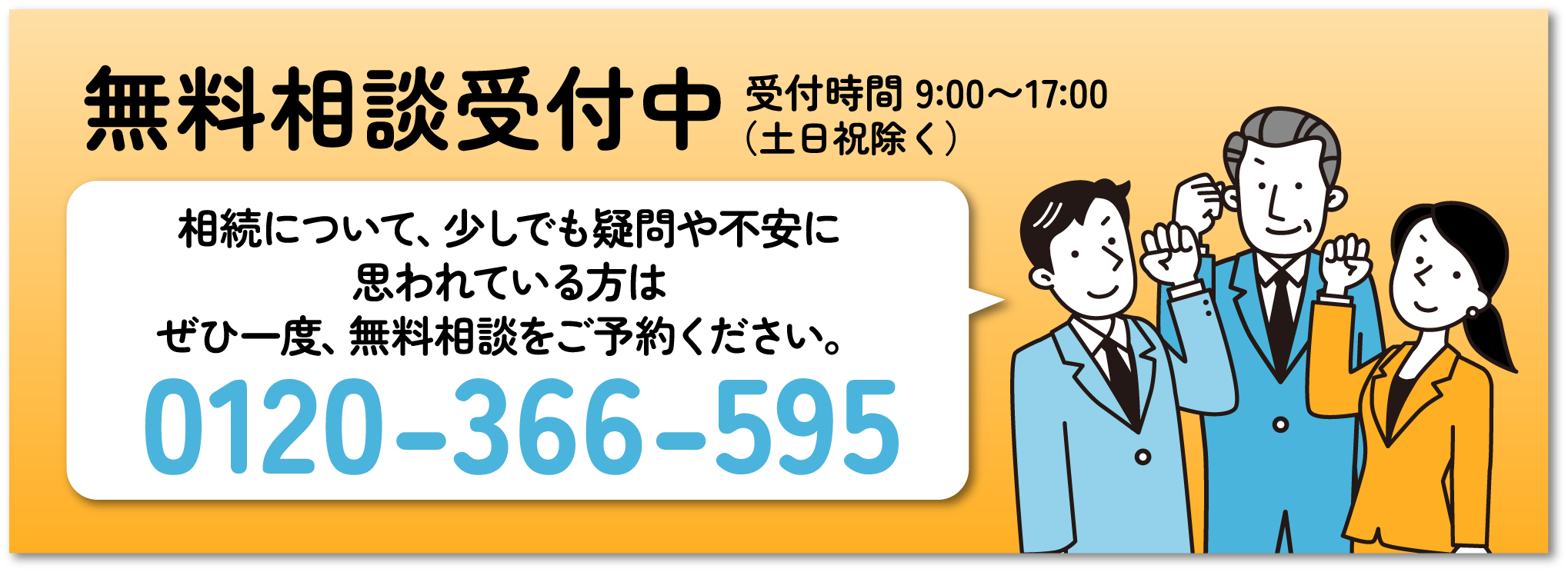

 通話無料
通話無料
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ