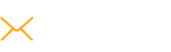相続コラム
2025/11/17 相談事例
万能ではなかった公正遺言証書
ご主人が亡くなられたとのことで、徳田さん(仮名)からご相談がありました。相続人は、徳田さん本人と、長女と次女の合計3人。
戸籍謄本をお持ちでしたので確認してみると、被相続人であるご主人は以前に一度婚姻歴があり、相談者とは再婚でした。つまり、徳田さんは後妻であり、他の相続人である長女と次女は前妻の子でした。長女は既に婚姻し、他府県で生活をしていますが、次女は独身で、被相続人名義の自宅で生活をしています。徳田さん自身は、次女と同じ町内の別宅(夫婦の共有名義)で生活をしています。
被相続人は、自身の相続において、相続人は前妻の子と後妻の間で揉める可能性があることを想定していたためか、公正証書遺言を作成されていました。そのため、徳田さんからの相談内容は、公正証書遺言に従って相続手続を行いたいとのこと。
公正証書遺言には、配偶者である徳田さんには「共有名義の土地と建物と田畑(5筆)と預貯金の全部」、長女には「田畑(2筆)」、次女には「自宅と田畑(8筆)」を相続させる旨が記載されていました。
公正証書遺言が存在するため、手続自体は特に問題なく進めることができるのではと思っていましたが、やはり問題となったのは、相続人同士の人間関係。といっても、前妻の子(長女・次女)VS後妻という図式ではなく、前妻の子の次女だけが、徳田さんに対して悪意をもっているとのこと。一方、長女との関係は良好で、現在も連絡を取り合っている関係です。
不動産の名義変更を行うためには、取得者からの登記申請が必要となります。今回は相続人全員が不動産の取得者であるため、司法書士は全員からの委任を受けなければいけません。ところが、次女は、徳田さんが公正証書遺言をもっていることに対して気に入らないためか、一切手続に協力しようとしません(次女の遺留分は侵害されていません)。連絡をしても一切拒否という状況です。長女の協力を得て、次女と話をしてもらいに行きましたが、それでも門前払いという結果に。
このままでは手続きを進めることができないため、徳田さん、長女と話し合った結果、二人の不動産だけ名義変更し、次女が取得する不動産については、心の整理がつくまで保留ということになりました。
本来、公正証書遺言を作成しておくことは、相続人同士で争うことなく遺産を相続することができます。しかし、相続人同士の人間関係に問題がある場合は、単に公正証書遺言を作成することだけでは解決しない事例もあります。
少なくとも、被相続人が生前、次女に対して「遺言書がある旨、相続人同士で仲良くして欲しい旨」などを伝えていたら、事態はもう少し変わっていたのかもしれません。 (496)


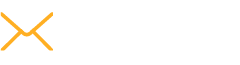
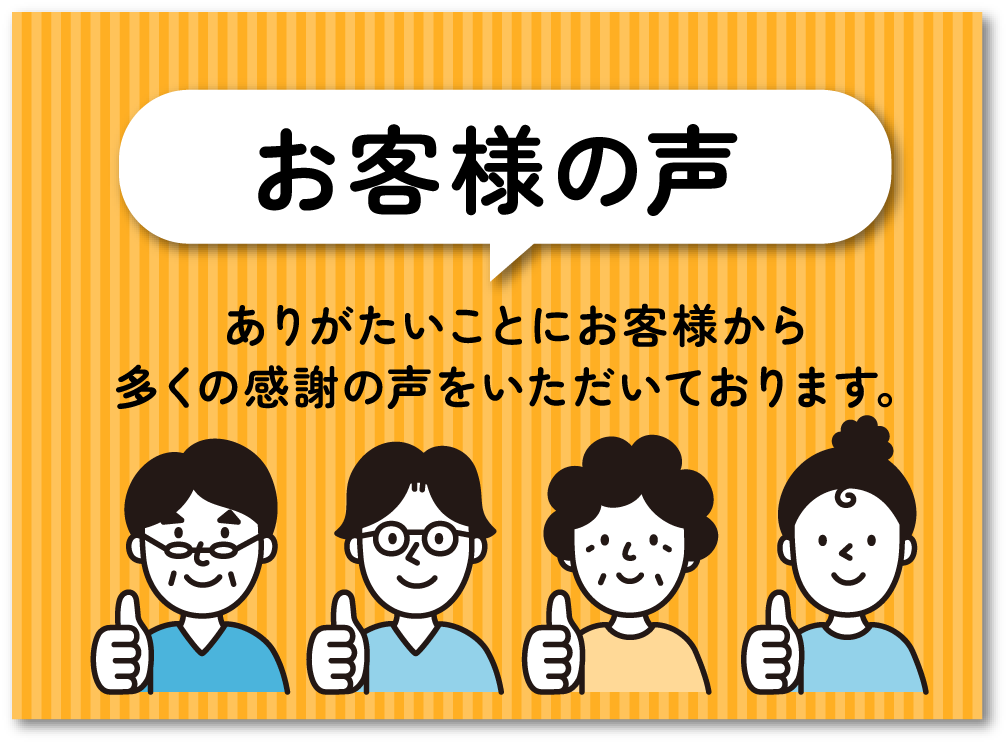
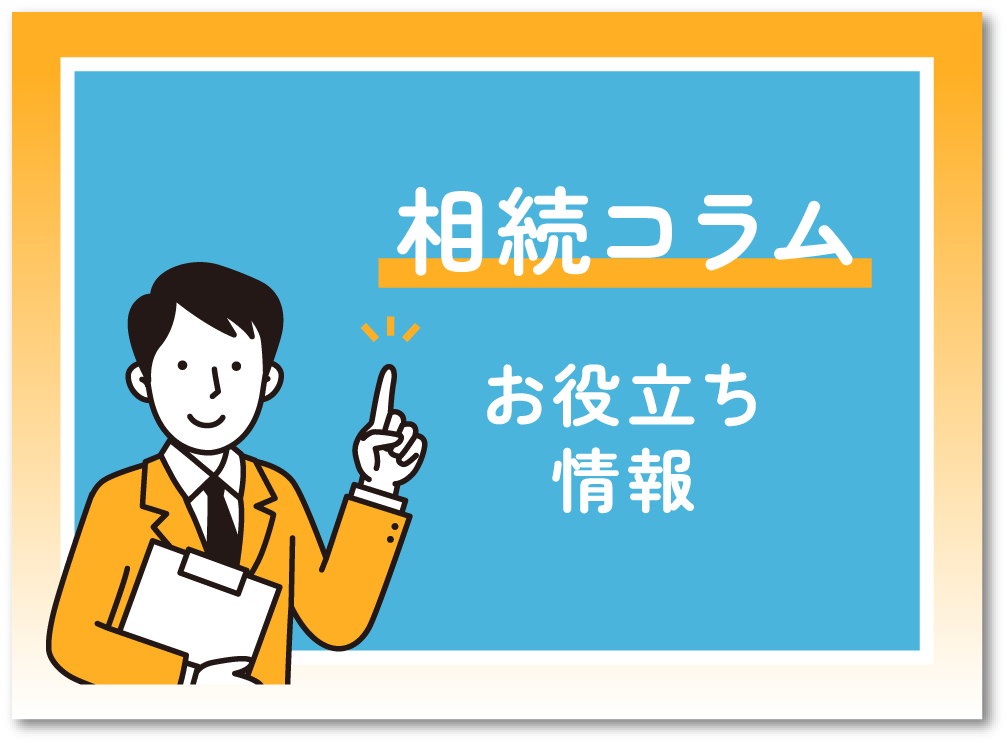

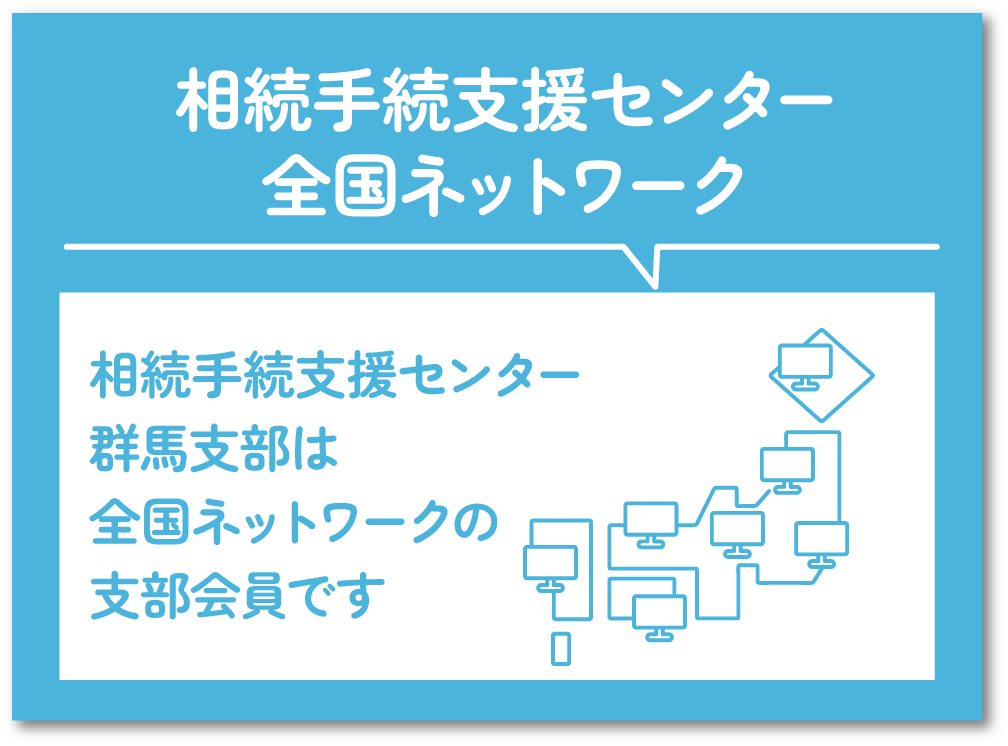
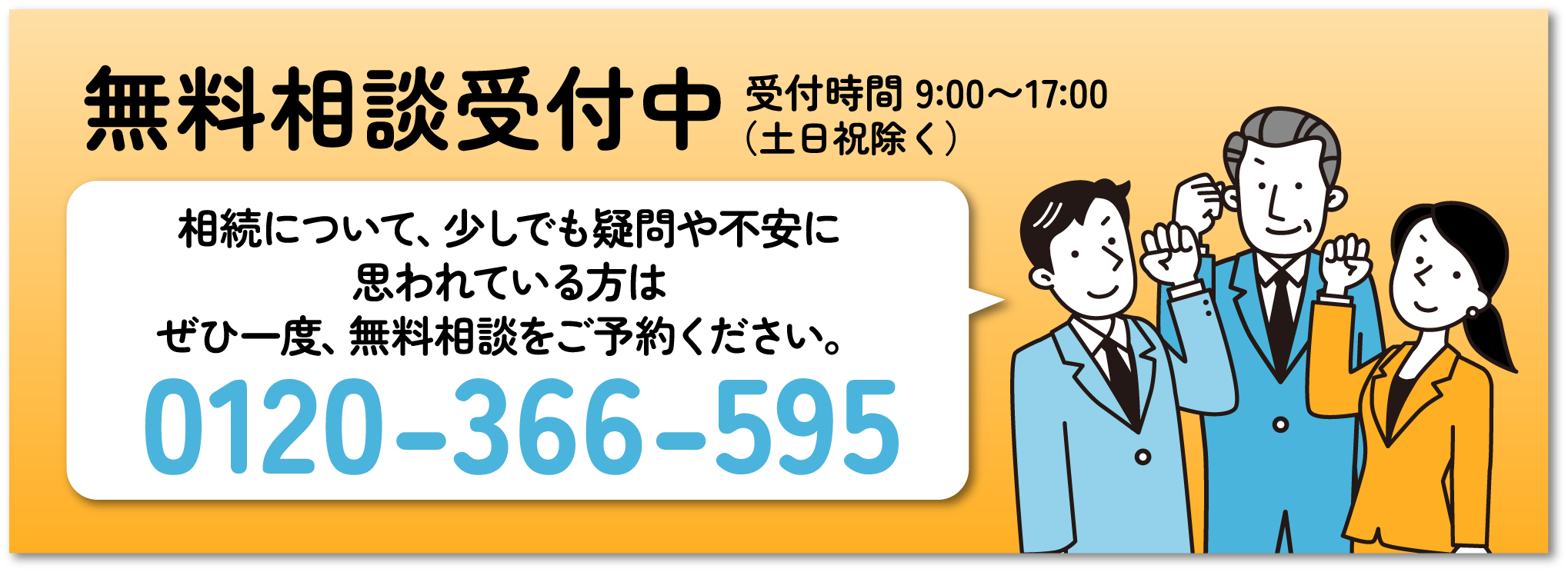

 通話無料
通話無料
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ